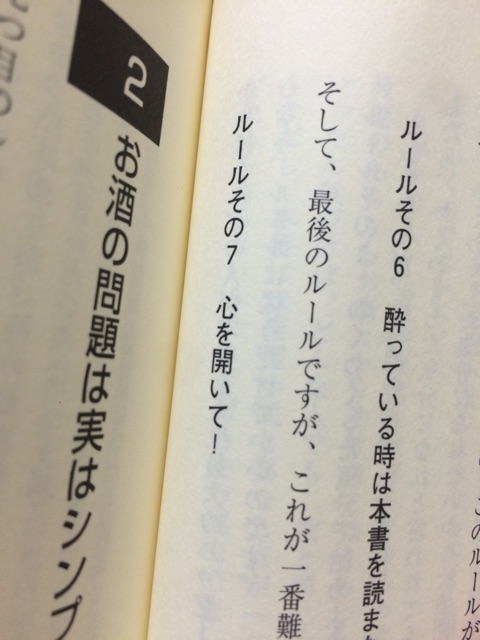7時。健司のいつもの起床時間だ。
もう何年も前から目覚まし時計がなくてもほとんどぴったりこの時間に起きるようになっている。
腰に負担がかからないよう、横を向いて手をつきながらゆっくりと起き上がると、隣で寝ている雪子を起こさぬようそろりと布団から出た。
台所で一人分のコーヒーを淹れ、椅子に座ってテレビを見る。朝食は食べない。
以前は雪子が健司よりも早く起きて焼魚やら味噌汁やらを作ってくれていたのでありがたく頂いていたが、最近の雪子は午前中いっぱい眠りこけているので、健司もわざわざ一人分の朝食を用意するのが面倒くさく、朝はコーヒーだけという生活が続いている。
テレビ画面の中では、昨日起こったという殺人事件のことや、人気芸能人カップルの破局、梅の花の開花状況に至るまで様々な情報が目まぐるしく流れ、そのたびに表情をころころと百面相のように変えて原稿を読みあげるアナウンサーを、健司は半ば感心する思いでぼうっと眺めていた。
8時15分。少し早いがそろそろ川中接骨院へ行く準備をする。
ここの院長の川中は地域で有名な腕利きの整体師で、予約は受け付けないので少し早めに行って整理券をもらうのだ。
それでも一時間は待つが、並んでいる顔ぶれは皆ほとんどが顔見知りで退屈はしない。
健司が通い始めたのはつい最近だが、早くも腰の具合が良くなってきて効果を実感している。
コートを着てマフラーをして、まだ眠っているであろう雪子に小さな声で「行ってきます」を言った。
接骨院へ行く道の途中にある小さな公園を通りかかると、梅の木が白い花を咲かせていた。
梅は雪子の好きな花だ。毎年梅が咲き始めると、「春の匂いがする」と言って喜んでいたものだ。
隣町の「梅まつり」にも二人で何度か訪れたことがある。
健司は毎年この時期は花粉症のため、「春の匂い」どころではないのだが。
接骨院に着くともうすでに先客が何人かいた。
健司は顔見知りの工藤という男の横に座っていつものように世間話をしながら時間を潰した。
「それにしても、ここ、物がいつも散乱しているよなあ。」
健司はせまい院内を見回しながらそう言った。
そこかしこに院長の私物らしき荷物が置かれており、ごちゃごちゃとしているのだ。
「だよねえ。この前も客の誰かが院長に『少しは片付けたら?』なんて言ったら、『ここは俺の接骨院だから文句のあるやつはこなきゃあいい』なんて言ってがはがは笑っていたよ。」
「そんなんでよく商売が成り立つよなあ。」
「まあそれだけ腕がいいからねえ。」
「こんなの雪子が見たら我慢できずに片付けちまうだろうなあ。あいつはきれい好きだから。」
「…あはは。そうかもねえ。」
工藤が健司の言葉に苦笑いをしていると、「工藤さーん」とちょうど彼の名前が呼ばれ、「じゃあ、お先に」と言って施術室の中に入っていった。
10時半。施術が終わって院の外に出ると、さてどうしたものかと健司は考えた。
家に帰ってもまだ雪子は寝ているだろう。
院長の施術のおかげで腰の調子も良いことだし、駅の方まで足をのばして「このは」にでも寄って行こうか。
うん、それがいい。そこで早めの昼食もとってしまおう。
「このは」は健司いきつけの喫茶店の名だ。店のオーナーは健司の同級生で、今はその娘夫婦が店をまわしている。
ここのナポリタンは絶品で、ときどき無性に食べたくなる。以前は雪子と一緒によく訪れていた。
健司が「今日はナポリタンが食いたいなあ。」と言うと、雪子は「あんたも好きねぇ。」などと言ってニヤニヤしながら、「じゃあいきましょうか!」と言って健司よりも張り切って出かける準備をしていたものだ。
「喫茶このは」と書かれたガラス戸を開けると、「いらっしゃいませ!」という元気な声で迎えられた。
オーナーの娘である明美は、客が健司だと分かると、「あら、中原さんいらっしゃい!」と愛嬌のある笑顔で彼の名を呼んだ。
「久しぶり。ちょっとお昼には早いんだけどねえ、食べに来たよ。」
健司が挨拶をすると、どうぞどうぞとカウンターのいつもの席に案内される。
少ししてお目当てのナポリタンが目の前に運ばれてくると、その懐かしい匂いになんだか胸の中をぎゅっとつかまれる思いだった。
ここに、雪ちゃんがいればなあ。
皆の前では言わないが、健司は二人きりのとき雪子のことを「雪ちゃん」と呼んでいる。
出会ったころからずっとそうだ。
雪子はいくら歳を重ねても、たとえ手や顔にシワがたくさん出来ても、それでも「雪ちゃん」と呼ぶのがふさわしいような、そんな女性なのだ。少なくとも健司にとっては。
今度来るときは雪子も一緒に来れるだろうか。
そんなことを考えながらもしゃもしゃとナポリタンを食べていると、手が空いたらしい明美が健司の横にきて話しかけてきた。
「どうですか、久しぶりのナポリタンは?」
「相変わらずうまいねえ。お父さんは元気にしているかい。」
「ええ、もう元気元気。今日も仲間と山登りだとか言って出掛けていきましたよ。」
「そうかい。そういえば俺も前に誘われたなあ。腰がもう少し良くなれば行けるんだけど。」
「なんか家にいるのが退屈みたいで、すーぐ外に出てっちゃうんですよ。」
「わかるなあ。俺も最近は雪子がなかなか起きてこないんで、家に居てもやることがないんだよなあ。あいつも身体が少し辛いんだろうから、こちらの都合で起こすのも可哀想だしね。本当はこのナポリタンも、一緒に食べに来たかったんだけど。」
健司があははと笑いながら言うと、明美は少し暗い顔をして、「そうですよねえ」と応えた。
ナポリタンを食べ終えた健司がご馳走様を言って店を出ようとすると、明美が深刻な顔をして健司に言った。
「あの、中原さん、もし何か困ったことがあれば、何でも言ってくださいね。あの、うちも…母を亡くしてますし、その…なにかと大変でしょうから。」
「ありがとう。心配してくれて。何かあったら遠慮なく言うよ。」
健司がそう言っても明美の顔から心配の色は消えなかったが、最後には再び笑顔を見せて「またいつでも食べに来てくださいね」と言って見送ってくれた。
12時。今から帰ればちょうど雪子が起きる頃だ。帰ろう。
「ただいま。」
玄関から健司が声をかけると、静まり返った部屋の中から雪子の声が返ってきたので健司は嬉しくなった。
「川中さんのところに行ってきたよ。あと、久しぶりにこのはにも行ってきた。」
健司のその言葉に雪子は特に反応せず、ソファーの上でごろんとなっている。
「雪ちゃんの好きな梅の花も咲いていたよ。ほら、あそこのケーキ屋の隣の、小さな公園があるだろう。」
雪子がこちらを向いて返事をした。
やはり梅の花が好きなのだ。
「昔はよく、二人で梅まつりに行ったよなあ。なあ、雪ちゃん。このはの明美ちゃんが、雪ちゃんのことを心配していたよ。だいぶ長いこと、顔を見せていないもんなあ。なあ今度、顔を見せに行こうか。」
健司がそう言うと雪子はうふふと微笑みながら曖昧な返事をした。
「なあ、雪ちゃん。身体の具合が良くないのかい。俺たちも、もういい歳だもんなあ。最近は雪ちゃんが眠ってばかりいるもんで、俺は暇で暇でしょうがないんだ。なあ雪ちゃん。もう少し暖かくなったら、また一緒に出掛けたいなあ。」
健司がそう言うと雪子は再びうふふと微笑み、やはり曖昧な返事をした。
「梅はだめでも、桜が咲く頃にはまた二人で…なあ、雪ちゃん…」
健司は雪子の隣に座り、気持ちよさそうに伸びをする彼女の頭を撫ぜながら、窓から流れ込む暖かい日差しを浴びて少しの間目をつむった。
**
春の訪れを感じるような暖かい日差しを浴びて、健司と雪子は二人並んで歩いている。
見慣れた街の風景だが、そこを歩く二人の姿がだいぶ若く見えるのは夢の中だからだろうか。
道端に見慣れないダンボールが置かれている。
二人が中をのぞくと、中にはちいちゃな子猫が入っていた。
捨て猫だということがわかると、雪子はすぐにダンボールを持ち上げて、うちへ連れて帰ると言う。
言い出したら聞かない性格だ。健司には反対する理由もなく、すぐに猫を飼っている知人に電話をしてアドバイスをもらい、病院に連れて行ったり、ペットショップへ走ったりと奔走した。
「ねえ見て、この子のここの部分、梅の花みたいよ。」
子猫は全体的に茶色っぽい色をしていたが、背中の部分に白い模様がついていて、雪子にはそれが梅の花に見えると言う。
「じゃあ、ウメって呼ぼうか?この猫。」
健司の提案に雪子は「ひねりがないねぇ」と言ってころころと笑った。
そしてひとしきり笑ったあと、「うん、とてもいい名前。ね?ウメちゃん。」といって子猫の背中を撫ぜた。
優しい眼差しで子猫を見つめる雪子の横顔になんだか懐かしい気持ちを抱きながら、健司も子猫の背中を撫ぜて名前を呼んだ。
「雪ちゃん。」
言った瞬間に視界がぐにゃりとゆがむ。
遠くから雪子の声がする。
「違うわよ、雪子はわたし。その子は、ウメ。」
**
「雪ちゃん」
健司が伸ばした手は空を切った。
気づくと部屋の中がオレンジ色に染まっている。どうやら眠っているうちに夕方になってしまったようだ。
健司の膝の上ではウメが静かに寝息を立てていたが、雪子の姿はどこにもなかった。
どこかに出かけたのだろうか。近所のスーパー?それとも、ずっと遠く?
そうか、俺が昼間一人でこのはへ行ってしまったのが悔しくて、あいつもナポリタンを食いに行ったのだな。なあんだ、だったら無理にでも起こして、二人で行けばよかった。
夢と現実とがごちゃまぜになったまどろみの中で、とても大事なことを思い出すように、健司はもう一度、彼女の名を呼んだ。
雪ちゃん。
夕陽のオレンジが一層強くなり、健司とウメを優しく包み込んだ。
健司は雪子の好きな梅模様を探そうとして、夢の中で見たよりも随分と大きいウメの背中に手を置いたが、その前に視界が滲んでしまってもう全然だめだった。
【第5回】短編小説の集いのお知らせと募集要項 - 短編小説の集い「のべらっくす」
参加しますにゃ

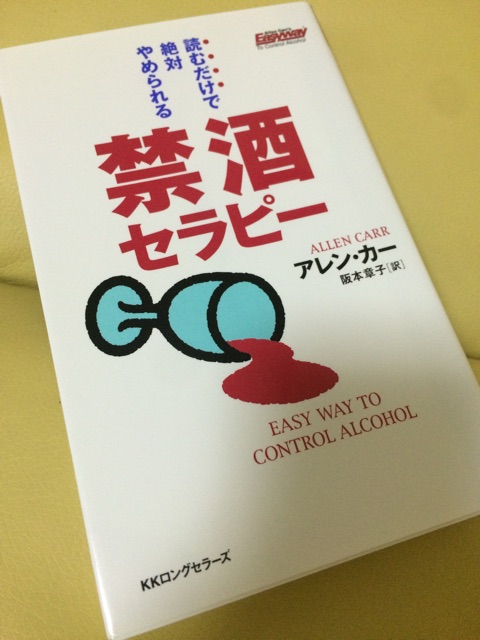
![禁酒セラピー [セラピーシリーズ] (LONGSELLER MOOK FOR PLEASURE R) 禁酒セラピー [セラピーシリーズ] (LONGSELLER MOOK FOR PLEASURE R)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41skKN7uKzL._SL160_.jpg)